
国際協力への興味は、大学入学後に海外に渡航した体験がきっかけであると記憶しています。中学・高校時からいつか海外に行ってみたいと夢見ていたため、大学1年の夏休みに初めてパスポートを取得し、単身ニューヨークへ旅行しました。当時話題になっていた、英語力を駆使して米国の投資銀行で活躍する日本人ビジネスマンを題材にした小説を読んで、漠然と成功モデルとして憧れていたため、実際に現地を訪れて雰囲気を体験してみたいと意気込んでいました。
夢にまで見た海外の空気は刺激的で、タイムズスクエアを訪れた際は鳥肌が立ったのを覚えています。ところが、楽しい思いも束の間、渡航中に世界金融危機が発生し、現地では只ならぬ雰囲気が漂い始めました。ウォール街を散策すると、倒産した企業の看板の付け替え工事が行われており、現地の新聞・ニュースでも投資銀行への批判の声が連日報道されていました。この大学1年時の出来事をきかっけに、成功モデルとして憧れを持っていたキャリア像にやや疑問を持ち始め、徐々に社会貢献を目的とする国際協力の分野に興味を持つようになりました。
幼少時から国連や世界銀行の存在は知っていたものの、日本のごく一部のトップエリートや政府高官が活躍する遠い世界であると思い込み、当初は考え付きもしませんでした。ところがネット上で調べてみると、国際機関で勤務する邦人職員のインタビュー記事や経歴が次々に見つかり、もしかしたら自分でも挑戦できるのではと思うようになりました。
大量の邦人記事を読み込んだ後、ある国際機関で勤務される方に失礼を承知で突然メールを送ってみました。するとその方から1ヶ月後に丁寧なお返事が届き、3つのアドバイスを頂きました。①国際機関勤務には大学院修士号が必要であり、可能であれば海外の大学院に進学するべきであること、➁国際機関では多様なバックグラウンドを持つ職員と勤務するため、欧米のみならず様々な文化圏の価値観への理解を深めること、③国際機関は即戦力を求めているため、事前に社会人としてある程度経験を積んでおいた方が良いことの3箇条を頂きました。この出来事をきっかけに、「国際機関を目指そう」と志すようになりました。
先ずは具体的な行動に移そうと、上記➁のアドバイスを前提に、それまで英語圏への交換留学を目標にしていたものの、より馴染みのない異文化に留学しようと軌道修正しました。当時、国際政治において中東におけるイスラム過激派やテロ問題に注目が向いていたこと、また経済分野でもドバイの発展に注目が集まっていたため、欧米とは大きく異なる中東の文化・イスラム思想に対する理解を深めたいという思いを持ち始めました。そこで外務省公募のクウェート政府奨学金を通じて、1年間現地の大学に留学しました。
国際協力分野では、各国政府間を調整する国連が最大の組織であると考えていたので、一番の目標は当初から国連でした。また、学部卒業後に海外大学院(ジュネーブ)に進学すると、ほとんどのクラスメートが将来的に国際機関で働きたいと希望しており、 周囲からの影響でより一層自分も国連を目指そうという思いが強くなりました。
とはいえ、国連は新入社員を養成する機能はなく、即戦力として入るべき場所であると理解していたため、先ずは民間企業で経験を積むことを選択しました。大学院から帰国後、東京の外資系通信社に就職し、金融機関やトレーダー向けに経済指標・貿易統計等のデータ管理を担当していました。その後、よりクライアントと対面して業務課題を解決していく仕事の経験を積みたいと思い、外資系コンサルティング企業(金融セクター担当)に転職しました。このような会社員勤務時も一貫して将来は国連へと計画を立てていました。
会社員として金融業界を支援する仕事をしていたので、将来は国連で持続的な金融(sustainable finance)関連の仕事に就きたいと考えていました。社会人5年目の年にいよいよJPOに応募しようと考えていたところ、その年に偶然国際労働機関(ILO)ジュネーブ本部にて持続的な金融のJPOポストが公募となり、試験を受験しました。
その後無事に選抜され、ILOに入局してみると、当該ポストは持続的な金融に関する部署横断的なイニシアチブを担当するもので、専門的な調査や案件形成を取り扱う「テクニカルな部署」と対外パートナーシップ・資金調達を担当する「管理部門」の2つの部署に50%ずつ所属する特殊な勤務形態でした。仕事を進めるうちに、加盟国政府との拠出金調整をすすめる後者の部署への関心が高まり、当該部署へ100%内部異動しました。会社員時代に様々な部署・関係者を取りまとめる調整業務を中心に経験していたため、テクニカルな部署で特定の分野の専門性を高めるよりも、全体調整を取り仕切る管理部門の方が自分の特性が合っていると感じたことも異動の理由でした。
その後、JPO3年目に現在所属している国連薬物犯罪事務所(UNODC)の正規ポストに応募し、無事に選抜されて引き続き対外関係の業務を担当しています。JPO任期中は興味関心のある様々な国際機関やポストに応募しましたが、結果的に前職の専門性と最も近いUNODCのポストで順調に選考が進んだため、現在の仕事に就いているというのが経緯です。
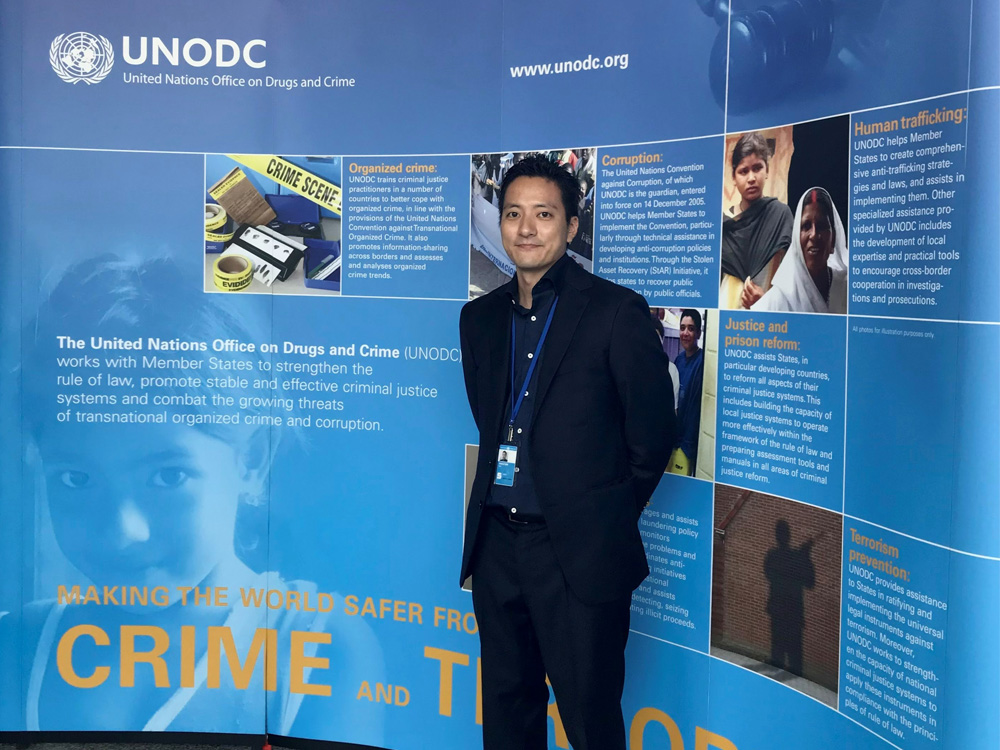
会社員として勤務した経験、特にコンサルティング企業での経験は非常に役に立っていると感じています。顧客企業に常駐して日々業務の課題や長期的な目標に向かって共に汗を流す仕事ですが、時間の制約・プレッシャーがある中で一定の成果を出す姿勢や複雑な事象をロジックをもとに紐解いていく思考法を鍛えられ、現在の国連の仕事でもスキルとして役立っています。
また、個人的には日本という場所で勤務していた経験が現在でも財産になっていると感じています。国連に入ると多様なバックグランドを持つ職員と協調して勤務したり、様々な意見が飛び交う混沌とした状況を交通整理して纏め上げるなど、国際的な仕事ならではの能力が求められます。実際に、圧倒的なコミュニケーション能力を活かして案件を推進する強者はたくさんいます。一方、「仕事の品質」という観点では日本の基準が遥かに凌駕していると感じています。様々なリスクを想定して事前に綿密な計画を立てたり、正確なデータを収集・加工するなど、細部にわたり成果物の質を高める志向は、日本ならではの強みであり、周囲への信頼につながります。日本基準の品質を目指すマインドセットは、他国出身の職員と差別化する上での武器であると感じています。
自分の経歴・専門性・強みを深堀りし、試験に臨むことが必要です。その際には自分自身で「なぜこの機関を目指すのか」「なぜこのポストに応募したいのか」「今までの経験をどのように活用するのか」「JPO後にはどのように国連で生き残る計画なのか」などを何度も自問自答して準備すると良いと思います。このように自分の過去や未来をしっかりと直視して現実的な計画を練り上げることは、試験対策としてのみならず、その後のキャリアの準備においても重要であると思います。
時折JPO試験を目指している方々から連絡が届き、様々な相談を頂くことがあります。その際、どの程度準備を進めているか、どれくらい深く考えて計画しているのかということがメールや会話の内容から非常に良く分かります。会話を通じて、この人は受かるだろうなと直感する場合は、結果的に合格されているケースが多いです。試験に向けた準備段階では5W1H(What, When, Why, Who, Where, How)を繰り返しながら応募用紙を何度も加筆修正し、それを面接というプレゼンの場で要約し、かつ論理的に話せるようアウトプットの練習を重ねることがカギであると思います。
(1)仕事内容の適性・(2)直属の上司との相性・(3)部署の方針の3つを注意深く観察していました。(1)自分の経歴・特性をフルに活かしてチームに価値を出すためには、自分に合う適材適所の仕事に就いていることが最善です。(2)また仕事の内容が自分に向いていても、直属の上司との相性が悪いとチームへの貢献が十分に認知されなかったり、ミスコミュニケーションの連続でモチベーションが下がってしまいます。(3)最後に、部署全体の方針としてJPOをどのように捉えているか見極めることが大切であると思います。一定期間のみチームを支援する一時的な人材であると見なされているのか、或いは今後将来的に組織に残り続けてキャリアを構築してほしいという育成人材と見なされているのか、JPO後に契約を続けられる可能性が高いのは明らかに後者です。部署の方針を把握することは、JPO後の生き残り方に大きく影響が出る重要な観点であると思います。
上記の3つの観点のうち、半年或いは長くても1年ほど過ごして2つ以上の項目が「赤信号」であると判断した場合は、自ら何らかの計画を立ててアクションに移した方が良いかもしれません。まず周囲に相談したり、自分自身でキャリア戦略を練り上げ、上司に別の仕事への担当変更をお願いしてみたり、部署内の別チームへの同時参画による兼業を自ら提案するなどの試行錯誤で活路を見出すことが出来るかもしれません。万一そもそも部署の方針・財務状況により、JPO後の契約の可能性が限りなく低いと判明した場合でも、積極的に他機関へ応募しながら、同時に所属機関内の別部署・フィールド事務所等で仕事を得る可能性がないか探る等、様々な知恵を絞ってアクションに落とし込めると思います。私の場合はJPO任期中、上司との相性は非常に良好であったものの、上記(1)と(3)の側面にリスクを感じて、上述の通り内部異動しました。
対外パートナーシップ・資金調達のポストでは様々な関係者の調整業務を担当するため、人間関係には非常に苦労しました。そもそも拠出金という「カネ」に関わる業務のため、各関係者がそれぞれの思惑や利益を念頭に相談を持ち掛けて来ます。課長間の社内政治に巻き込まれたり、同僚からやや圧力を感じることもありました。
それらに対処するため、調整役として正しい方向性・あるべき姿を常に思い出しながら、時には毅然と対応して「NO」と伝えたり、また時には課題に頭を悩ます同僚に手を差し伸べて柔軟に対応したりと、バランス感覚を保ちながら拠出金獲得・開発協力の案件形成を支援していきました。調整役として関係者全員がある程度納得する形で着地点を目指す作法を学び、非常に良い経験になったと思います。
(A)確実に取れるポストを1つ用意しておくこと、(B)同時に挑戦案件として様々なポストに応募することが重要であると思います。(A)について、私の場合はILOの所属部署において、JPO1年目から徐々に上司に将来契約の打診を始め、3年目延長に入る際にその後4年目に正規職員として契約を結ぶ可能性が極めて高いという確信を得ました。確実に取れるポストを用意しておくことが何よりも最優先事項であり、この交渉作業をないがしろにして闇雲に過ごしてしまうと、JPO期間の後半に差し掛かるにつれ、追い詰められてしまうと思います。まずは1年目に信頼を得て自分の居場所を固め、2年目に部署にとって必要な人材になり、3年目の延長に入る場合は部署にとって不可欠な主要メンバーの一人として仕事内容・社内ネットワークに精通するというように、段階的にポストの可能性を高めていくアプローチが肝要であると思います。
(B)について、上記の通り私の場合はILOの所属部署で確実に取れそうだというポストがあったものの、ほぼ確実にJPOから引き続きP2レベルのままでの契約となることが分かっていたこと、また仕事内容に慣れてしまい、新たな挑戦をしないと4年目以降にモチベーションが保てそうにないという思いがあったため、同時に挑戦案件として他の国連機関のP3レベルポストへの応募を続けていました。もちろん、この挑戦案件はあくまでも比較的可能性の低いものに対して挑むことになるため、残念ながら応募努力が報われないケースがほとんどです。したがって、優先度でいうと(A)の次に劣後させて時間や労力を割いていました。
最後に、よく国連界隈で話題に上がる「コーヒータイムなどを通じたネットワーキング努力」について、あくまでも個人的な考えとして、JPO1年目の時点でネットワーキングを重視する必要は余りないという方針で動いていました。それよりも目の前の仕事にしっかりと取り組み、部署の仕事内容や開発協力の仕組みへの理解を深め、一日でも早く戦力として価値を出そうと没頭することが大切ではないかなと思います。それにより部署での信頼が高まり、「(A)確実なポスト」の可能性を限りなく高めようという計画で過ごしていました。もちろん、人によっては積極的なネットワークがキャリアにつながったという声も聞きますので、ケースバイケースで状況を見極めて、より最適な行動を取っていくことが望ましいと思います。
職種自体は引き続きドナー政府との対外関係や資金調達を担当しており、JPO時代から大きな変化はありません。一方、所属機関は「専門機関」から「国連事務局グループ」の傘下に移り、制度・文化など差異を感じています。例えばドナーとの拠出金調整の際に、専門機関ではやや例外的な対応が発生する場合も、機関内に所属する法務・財務・人事担当者と相談の上、比較的柔軟かつスピード感を持って解決していくことが可能でした。
一方、多数の機関を抱える事務局グループでは全体で厳格に規定されているルール・規則があるため、基本的にはルール順守が求められます。それでも例外が発生する場合はニューヨーク本部に判断を仰ぐことになり、手続きに時間を要することがあります。このような内部調整・事務手続きに手間取ると、現地受益者に対して迅速な還元を目指すことは困難であり、案件に携わる各関係者にとって望ましくない結果となってしまいます。したがって、合意文書のドラフトや開発協力の案件形成の段階においてそもそも例外ケースが発生しないよう、事前に関係者と時間を取って協議し、相手を説得して合意する根回しのスキルが今まで以上に求められていると感じています。
また、職位ではJPOから正規職員となり、この点でも違いを感じています。もちろんJPOは任期中に責任ある仕事を任されますし、給与を受け取っている以上、一定の成果を求められます。しかしながら、赴任直後はお客さん扱いされる側面がありますし、仕事がいきなり降ってくることもなく、最初はやや手加減されていたと思います。一方、正規職員となるとそのような手加減は一切なく、赴任当日から業務を任されます。引き継ぎやキャッチアップ期間などもなく、即座に戦力となることを求められます。このように正規職員(特に別機関に移籍した場合)となるとやや厳しい側面がある一方で、特定分野における一人のプロ・専門家として頼りにされるため、より一層仕事のやりがいがあると感じています。
午前中は9時に出社すると、東南アジア・南アジア地域やアフガニスタンの同僚(時差の関係で現地は既に午後)からメールが入っているため、即座に対応します。その後ウィーン本部の各部署の同僚やアフリカ地域の同僚から徐々に相談のメールや電話が掛かってきます。午前10-11時頃は最も集中できる時間帯のため、会議を入れることが多いです。外部の政府代表部関係者や内部の同僚との会議に出席します。
昼食は基本的にオフィス内のカフェテリアで取りますが、時折気分転換を兼ねて同僚とオフィス外に出てドナウ川近辺のレストランで食べることもあります。また、ドナー政府の関係者とのワーキングランチが入ることもあります。ウィーン赴任直後は、お昼の時間帯に国連が提供するドイツ語講座を週2回受講していました。このように国連では各種言語のクラスが用意されており、非常に便利です。
午後はメール・電話対応や会議出席が落ち着くため、今後の会議に向けた調査や資料作りなどに没頭することが多いです。時期によっては事務局長の出張やドナー政府との会談が毎週のように入ることがあり、その場合は幹部向けのブリーフィングノートやスピーチ原稿等の作成に取り組みます。夕方になるとニューヨークや南米地域の同僚が出社の時間帯となり、再び問い合わせや相談のメールが入ってきます。繁忙期は残業することもありますが、基本的には18時に帰宅します。

開発プロジェクトに資金を拠出する各国ドナー政府・プロジェクトを実行するUNODCフィールド事務所との間に立つ仲介役として、案件形成・資金調達に関するコーディネーション全般を担当しています。具体的には、ドナー政府と相対するUNODCの窓口として、本部側で開発協力案件の予算金額及び合意内容の協議を進め、法務や財務を担当する部署の同僚と調整、同時に現地の地域・国別チームと連携を取ってプロジェクト案・予算案のレビューを実施し、案件形成を支援しています。プロジェクトが無事にローンチされた後は、突発的に発生する進捗課題やプロジェクト合意内容の修正・追加等について、両者の仲介役として対策を講じています。
また、ドナー政府とUNODC事務局長のハイレベル会議の調整・準備も担当しています。年間を通じて定期的に会談が予定されているため、各部署・地域事務所の意向を取り纏めてアジェンダ案を作成し、出席する幹部向けのブリーフィングノート・スピーチ案等を作成しています。上記以外には、ウィーン本部から外に出て出張することもあり、最近ではウクライナの首都キーウを訪問しました。当地における国境管理や腐敗等の課題を支援するため、各国ドナー政府の現地大使館との関係性強化に向けた協議を実施しました。このように、現状のパートナーシップを維持・強化しつつ、新たな資金獲得に向けて積極的に現地を訪問することも仕事の一つです。


一言で表すと「孤独感」と常に戦っていく必要はあるかなと思います。国際機関では、世界中から異なる文化・社会背景を持つ職員が集まっているため、言動も行動も千差万別です。そもそも職場というのはあらゆる年齢層の職員が各々のモチベーション、思惑、責任感などを持って時間を共有するため、人間同士の行き違いは自然と発生する場所であると思います。国際機関の場合はさらに文化の相違という変数が加わるため、職場の雰囲気はより一層混沌とします。日本では常識として共有している感覚も通じないことがあり、ミスコミュニケーションは日々発生します。そもそも価値観の共有が容易な職場ではないという前提を受け入れる必要があります。
また、国連での働き方は、基本的には個人ベースで働く場合が多いと感じています。部署内で自分の責任範囲・分野が割り当てられ、別の部署の同僚と協議し、外部関係者と会議を重ねるなど、自分一人で日々の業務を回していく働きが求められます。もちろん、重要な局面では上司に決裁を仰いだり、同じ部署の同僚に助言を求めることもありますが、基本的には個人で動いていくことになります。このように、多様性の中で「個」として力強く自律し、かつ前向きに働いていく姿勢を心がけています。文化の違いはあれど、やはり国連でも一緒に働いていて責任感があり、明るい性格の人は周囲から非常に頼りにされています。

コンサルティング企業で様々なプロジェクト・顧客先に常駐した経験は、どのような現場に送り込まれてもやっていけるという自信に繋がったと思います。スキルの面では問題解決の手法(複雑な事象を構造化したり、漏れなく重複なくロジックツリーを作成して施策を編み出す思考法)やプロジェクトマネジメントの調整業務を経験したことが、現在の国連の仕事でも非常に役立っています。
個人的にはより多くの民間企業出身者の方々に国連に入ってきてほしいと願っています。国連というと途上国現地で開発協力を進めていくイメージが強いかと思いますが、機関内には様々な部署があり、私の勤務している対外関係のポストや管理部門(財務・法務・人事・調達等)はまさに民間企業のスキルを直接活かせる仕事である思います。
仕事から離れて非日常的な活動をすることが一番ストレス発散になると思っています。例えば週末にハイキングに出かけて自然を満喫したり、休暇を取得して旅行するなどして気分転換しています。欧州に住んでいると比較的容易に国内を列車で移動したり、周辺国に旅行に出掛けることも出来るので、定期的にリフレッシュするようにしています。
仕事から離れて非日常的な活動をすることが一番ストレス発散になると思っています。例えば週末にハイキングに出かけて自然を満喫したり、休暇を取得して旅行するなどして気分転換しています。欧州に住んでいると比較的容易に国内を列車で移動したり、周辺国に旅行に出掛けることも出来るので、定期的にリフレッシュするようにしています。
国連ではそもそもワークライフバランスを保てるように勤務形態や機関内ルールが設計されていますので、この点はあまり苦労しないと思います。むしろ日本で勤務した経験のある方にとっては、あまりにもフレキシブルで驚くのではないかと思います。具体的には、毎年有給休暇が30日与えられ、多くの職員が夏期休暇で3-4週間ほど長期休暇を取得します。また、年末も12月下旬から年明けまでクリスマス休暇を取るパターンが多いです。
普段の仕事でも繁忙期を除いて基本的に局長や直属の上司を含めて多くの職員が18時には帰宅しますし、例えば19時まで残業するとオフィスの同じフロア内にほとんど人がいないことが多いです。もちろん、個人で業務の進捗や成果物について責任を負う自律性が求められますので、必要であれば自主的に平日・週末を利用して残業することもあります。
国連全体の財政・予算編成の仕組みに関する知識を増やしていきたいと考えています。これまで、専門機関であるILO、事務局傘下のUNODCにて一貫してドナー政府との関係性構築・拠出金調整を担当して来ました。このように、各機関における「任意拠出金(Voluntary Contribution)」の資金調達に関わる仕事をしてきたことになります。
一方、これらの各国連機関は加盟国政府から「分担金(Assessed Contribution)」も受け取っています。分担金は加盟国の支払い能力に応じて国連総会の第5委員会で毎年交渉・協議の上、決議されています。各機関内では、分担金は遠いニューヨークで協議されているもので直接関わりがなく、自分たちの交渉次第である任意拠出金(またそれに紐づく各プロジェクトの形成)の増減のみに注力しているのが実情です。
しかしながら、資金調達・拠出金調整に関わる者として、各機関の任意拠出金のみならず、国連全体の予算がどのように協議されているのか、加盟国間の分担率はどのように決まっているのか、また各国際機関への分担金の割当はいかにして決議されているのか等についても背景や構造の理解を深めていきたいと考えています。
JPOの任期を終え、現在所属の機関に移ってきた際は非常に苦労しました。別機関に移ったため、仕事の仕方や日々使用するERPシステムも前所属の機関と異なり、内部の組織図や人間関係の構築もゼロから再出発する必要がありました。それに加えて、上述の通り正規職員となると即戦力の扱いになるため、赴任当日から他部署より仕事の依頼が大量に降ってきました。引き継ぎは一切なく、上司や同僚も当該ポストの実務について詳細を把握していなかったため、様々なプレッシャーのある中で手探りで自力で解決していくという状況でした。
さらに追い打ちをかけるように、財務上の過去の遺産が見つかり、調査を進めると10年前から解決されずに積み上がっている課題であることが明らかになりました。ドナー政府からは早急に対処するよう要請が入る一方で、機関内では面倒な問題を明るみに出さないよう阻止しようとする動きがあり、板挟みになりました。このように赴任直後からやや後ろ向きな課題に対しても対処していく必要があったため、日々大変な時期であったと記憶しています。結果10ヵ月ほど掛かって調査作業や関係部署への説明を一歩ずつ進め、上層部・事務局長に最終報告が入り、無事に解決した際は「正しいことをした」という達成感がありました。国連機関の本部では華やかな側面ばかりではなく、このような泥臭い仕事もあるということは、事実としてお伝えしたいと思います。
業務上の課題・悩みは問題となっている事象の中身自体ではなく、「人間関係」に起因することがほとんであると考えています。国連ではさらに職員間の文化背景の相違が加わるため、何事も一筋縄には進捗しないと感じています。このような国際的な環境における人間関係への対処には教科書が存在しないため、常に自律的に創意工夫して解決していくしかないと考えています。この分野で困ったときはAさんが助けてくれる、逆にBさんに話を持っていくと毎回ややこしくなる等をトライ&エラーで学び、自分なりの人間関係マップを構築していく必要があります。
赴任直後は中々難しいですが、先ずは目の前の小さな業務を着実にこなして、徐々に実績を積み上げていくと周囲の信頼を得て、協力してくれる仲間を増やしていけると思っています。もちろん、自分が困った時にテイクをするばかりではなく、日頃から情報を提供したり、相手の課題を快く支援するなどのギブをすることで持ちつ持たれつの関係を作る努力も必要であると感じています。総じて、仕事に対して誠実に取り組んでいると、自然と周囲の信頼を獲得して、協力的な同僚の数を増やしていけると考えています。
国連の空席公募を見ていると、ほとんどのジョブディスクリプションで先ずは英語の能力が必須で、それ以外の国連公用語(中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語の5カ国語)が出来ると選考上有利であると記載されている場合が多いです。また、職種によっては特定の第二言語が求められている場合があり、例えば英語が必須で、かつフランス語が出来ると望ましい等の書きぶりになっています。またJPO試験でも英語能力が審査されます。以上のように、「英語能力」については国連で働く上では必要最低限のスキルであるため、留学などを通じて事前に習得する必要があります。
一方、実はそれ以外の言語については、国連の業務で必要であると感じたことがありません。空席公募の選考上では複数言語が出来ると有利になるため、就職活動の役に立ちますが、普段の業務自体は全て英語で行われます。実際、日々世界各地の同僚とビデオ会議やメールのやり取りをしますが、常に英語でコミュニケーションを取って進めています。ただし、フィールドの現地で活動する場合は特定の第二言語が必要になる場合があります。例えば西アフリカ地域で仕事をする場合はフランス語、南米地域に赴任する場合はスペイン語が出来ないと、現地の裨益者や政府関係者との意思疎通が困難で、業務に支障が出る可能性があります。あくまで個人的な見解ですが、英語のみが出来る職員は(本部を除くと)主にアジアや中東地域で活躍している印象を受けています。
英語の習得には特に力を入れていました。中学・高校では受験勉強を通じて英文法をインプットし、読解力の向上に専念していました。大学ではパスポートを取得して海外に渡航し、実際に生きた英語を体感して、リスニングやスピーキングを伸ばすことに注力していました。
上記とリンクしますが、やはり英語を積極的に勉強しておいたことは良かったと実感しています。大学生の時は国際機関を目指すために英語の習得に力を入れていましたが、結果的にその後就職活動の際にも大きく役立ちました。外資系企業の選考の際にも英語面接がありましたし、その後転職した際にも英語がビジネスレベルで出来るという理由だけで転職市場で非常に有利であると感じました。もちろん、社会人として働く上では総合的に様々な能力が必要ではありますが、英語はその中でも他者と差別化できる大きな武器であると感じます。結果的に目標であった国連に入ることにも繋がり、学生時代に英語に興味を持って勉強して良かったと思います。
大学学部に在籍していた際、日本国内にある国連大学高等研究所(UNU-IAS)にて数か月インターンをしました。大学内で募集しており、書類・面接選考を経て、同機関に派遣されました。インターン中は研究員のアシスタントとしてデータを調べたり、各国政府の政策文書を要約する等の作業を行いました。国連の関連機関に短期間携わることが出来たことは良い経験になり、上司である研究員及び共に作業を実施する同僚のインターン共に外国人のため、英語でコミュニケーションを取りながら業務を体験することも良い勉強になりました。
大学院在籍時は、金融情報やデータ分析を取り扱う業種の経験を得たいと思い、現地ジュネーブのヘッジファンドで半年ほど有給インターンをしていました。石油トレーダーの上司のもとで、エネルギー投資のデータ分析をしたり、顧客向けのプレゼン資料作成の補助を実施していました。その作業の際に、勤務先が加入している情報サービス(金融情報を検索・取得可能な便利なクラウドサービス)に興味を持ち、インターン期間中にこの金融端末を提供している外資系通信社の日本支社に応募し、大学院修了後に同企業のデータ管理部へ就職することになりました。
大学学部在籍時にネット上で国連職員の経歴を色々と調べていくと、多くの方々が欧米の大学院で国際関係、経済学、法学等の修士号を取得していることが分かり、その中で特に興味を持っていた国際関係分野に絞り込んで進学先の候補を検討しました。その際、先ずは米国の大学院を検討しましたが、学費や生活費等の費用が高額なため諦めることにしました。また、英国の大学院については修士号のカリキュラムが1年間のみで、可能であれば2年間海外で学びたい希望があったため、それ以外の選択肢を考えました。
最終的に国際関係学に強みを持つパリとジュネーブの大学院の2校に絞り込んで対策を進め、出願しました。自分がどの分野で勉強するかという興味関心が最も重要な検討材料ですが、同時に国際機関を目指す上でどの分野が最も有効か、将来につながるかという点も考慮して計画を立てることが大切ではないかと思います。当時は思い付きませんでしたが、今思うと国連の空席公募ページ上より各ポストのジョブディスクリプションを読み込んで、求められる学歴の分野を調べておく等、より踏み込んで調査することも進学先検討の際に有効な対策だったと思います。
結果的に出願した大学院に2校とも合格することが出来ましたが、両校ともに奨学金を獲得することが出来ず、日本政府所管の独立行政法人から奨学金(教育ローン)を借りることにしました。2年間の学生生活に必要な費用をシミュレーションした結果、当時パリの大学院は学費がやや高く、採算を合わせることが困難であることが分かり、ジュネーブの大学院に進学することを決めました。
私は奨学金を得ることが出来ず、教育ローンを借りることになりましたが、やはり可能であれば給付型の奨学金を取得するに越したことはないと思います。一方、奨学金を得ることが出来ず、それにより大学院進学を諦めるべきか迷っている方々もいると思います。難しい選択ですが、一つの例として私の場合は社会人5年目で全額返済することが出来ました。教育ローンを組んだ場合でも、しっかりと返済する意思を持っていれば早期に完済出来る点もお伝えしたいと思います。
JPO制度を通じて国連に入局した際は任期付きの契約に戸惑いましたが、現在では当たり前のように感じています。事実、現在所属している機関の職員の多くが任期付きの契約形態で勤務し、毎年契約を更新しています。もちろん、多少不便に感じる点があるのは事実で、毎年人事部との契約更新や、オーストリア当局との滞在許可書の更新手続きが発生します。とはいえ、国連の仕事は人事異動の制度がなく、常に自分で空席公募を見つけてキャリアを築いていく必要があるため、そもそも同一の勤務地やポストにて長年勤務することは望ましくないと思っています。したがって、任期付きの契約形態については特に気にする必要はないと考えています。
上述の通り国連では人事異動の制度がないため、キャリアパスも職員ごとに千差万別であると思います。キャリアの典型的なパターンや王道があるわけではないですが、一つの事実として中堅から管理職に上がる際には本部・途上国両面の経験が考慮されている印象を受けています。私の場合は今後引き続き国連でキャリアを築いていくのであれば、将来的にフィールドでの経験も積みたいと考えています。最も現実的なルートは内部異動で別のポストを経験することですが、別の機関も経験してみたいという思いもあります。いずれにしても常に内部での情報にアンテナを立てつつ、空席公募をチェックしてチャンスを逃さないことが重要であると感じています。
日本の会社員を辞めて国連に移った際は雇用形態の違いにやや戸惑いましたが、国連でキャリアを続ける以上は任期付きの契約を受け入れていくほかないと考えています。家族の事情など様々な不安があると思いますが、国際機関に挑戦するのであればある程度のリスクを取る必要があると感じています。
家族の事情は国連勤務では中々難しい点で、簡単な答えはないと思います。自分自身のキャリアプランや希望勤務地を追求しつつも、家族の思いを熟慮することが大切で、万一勤務地を変える場合は事前に家族と相談して決断する必要があると思います。職場の局長や課長などの経歴を見ると、多くのベテラン職員が長年のキャリアの途中で危険地域を含む途上国勤務を経験しており、一時的に家族と離れて生活していた方もいます。キャリアと家族のバランスは難しい点ですが、国連勤務では避けられないトピックであると思います。
上記と同様に家族としっかりと話し合って決断する必要があると思います。国連では世界各地へ移動する可能性がある一方、子供の教育費の補助金が支給される等、福利厚生は充実しています。例えば先日トルコで勤務している同僚と話していたところ、国連の補助金制度のお陰で、子供が2人とも米国の大学に通うことが出来たとのことでした。また、その他の様々な同僚の話を聞くと、家族を同伴して積極的にあらゆる地域に移動するケースもあれば、一方で家族(特に子供の小中学校の都合)を最優先に同一の勤務地に長年滞在する場合もあり、それぞれが家庭の事情を考慮してキャリアを選択しているようです。
今後将来的に、一度国連を出て日本の公的機関で勤務すること、或いは民間企業に戻って新たな経験・スキルを得ることも選択肢の一つとして検討しています。国際機関以外で経験を積むことは、その後再度国際機関に戻る場合にも活かされると思います。
海外で駐在員(Expat)として生活すると、赴任直後は純粋に楽しいのですが、徐々に心身ともにストレスが溜まり、疲れを感じることがあります。慣れ親しんだ母国から離れて暮らすため、非常に自然な反応であると思います。結論、勤務地を変えるたびに現地の生活や勤務先オフィスの社風に慣れていくしかないわけですが、その途中では様々な工夫を凝らしてストレスを管理する必要があると思っています。私の場合は普段から運動したり、日々睡眠をしっかり取るように気を付けています。
また、国連で勤務していると毎月「Home Leave(帰省手当)」のポイントが付与され、24か月分のポイントが貯まると、母国往復の飛行機代と交換出来る制度があります。私も以前この制度を利用して日本帰国の飛行機代を支給してもらい、実家に帰省してリフレッシュすることが出来ました。海外生活におけるストレス発散の最も効果的な方法は、定期的に日本に帰国することかもしれません。
36歳以上の場合は、現行のJPO制度には応募できないため、それ以外のミッドキャリア制度(下記の質問で回答)を利用するか、或いは空席公募に応募する方法の2つがあると思います。より確率が高いのは前者ですが、後者を通じて競争を勝ち抜き、中堅職を得ている方もいると聞きます。このような方々に共通することは、公的機関・NGO等で国連の業務に近い開発協力の経験を持っているか、或いは公認会計士などの資格を武器に民間で専門職の経験を積んだ上で国連に挑戦している点ではないかと思います。

定期的に外務省公募で国連ミッドキャリアレベルのポストへの公募が出ており、また国連外では世界銀行のミッドキャリア制度やリクルートミッションもあります。これら日本政府支援の制度に応募することが、選択肢の一つではないかと思います。通常、国際機関への転職は空席公募へのアプライのみであり、世界中の候補者と競争することになります。この点、幸運にも日本は上記の通り政府支援策があるため、これらの制度を最大限活用することが有効であると思います。
私は大学生の時に国連を目指そうと志しましたが、JPOとして採用されるまで準備に11年間を要しました。今思い返すと、当時の自分にとっては現実の目標として捉えることが難しく、目標というより憧れのような職業であったと思います。夢に向かって一歩ずつ進む中で、徐々に実現可能な目標になったと感じています。現在10-20代の方々はインターネットやソーシャルネットワークを活用して物事を迅速に、かつ多角的に調査することに非常に慣れており、強みがあると思います。国際分野に興味を持ったら、先ずは国際機関や邦人職員の記事などをネットやSNSで洗いざらい調べてみると、自分の興味関心に最も近い分野を見つけることが出来ると思います。
また、ネット検索のみならず、実際に外務省国際機関人事センターの公式ウェブサイト、Facebook、Twitterなどで告知されているキャリアイベント等に参加して、外務省や国連の職員の方々に直接会ってみると、さらに詳しいことが分かると思います。オンサイトで話を聞いたり、人と話してみると、より一層やる気が出てくるかもしれません。このように積極的にアクションを起こしていくと、夢が徐々に現実的な目標に変わっていきます。自分では到底無理だとは思わずに先ずは第一歩を踏み出して、是非運命を切り開いてほしいと思います。