
私が国際協力に興味を持ったのは、大学3年生で就職活動を意識し始めた時にJICAから出向でいらしている教授が担当する授業を履修したことがきっかけです。授業を通じて日本に研修で来ている途上国行政官の方々と話をし、途上国の開発課題に向き合う中で「自分のすることが直接人・社会のためになる仕事」に魅力を感じました。新卒で開発コンサルティング会社に就職をし、その後総合系コンサルティング会社の公共セクター部門に転職をしました。そこでアフリカにおける再生可能エネルギーに関する調査をしていたときに、世界銀行やアフリカ開発銀行などの国際機関の方々とディスカッションする機会がありました。その中で、国際機関ではさまざまな国、バックグラウンドの人がチームとして共通の目的に向かって仕事をしており、また国際開発にうまく新たな技術やビジネスモデルを組み込んでいると感じました。自分もそんな多国籍な環境で仕事がしたいと思い、国際機関を目指すようになりました。
これまでも公共セクターの仕事はしていましたが、公的機関に勤めたことはなく、実際に今国連で仕事をしていて、民間と公共の仕事の進め方の違いに苦労しているところはあります。ただ、民間、特にコンサルタントとして培った調査、分析、資料作成能力、Client orientedな姿勢は今の仕事でも役立っていると感じています。具体的には、ドナーの支援方針、プロジェクト対象国の開発方針・ニーズを調査し、それをパワーポイント等で視覚化する能力は同僚からも評価されていると感じています。プロジェクトのロジックを担保することは大切ですが、同程度にそれを「伝えること」は非常に重要だと感じています。
平均的な一日の仕事の流れとしては、時差の関係で朝はアジアのパートナー(ドナー、国際機関)とのミーティングをし、昼は支援国政府や他の国際機関が作成したレポートのレビュー等の書類業務、夕方はアフリカのパートナーとミーティングをすることが多いです。国連で仕事をする上で意識していることは、自分の裁量で進めるところと、関係者を巻き込みながら進めるところのバランスです。国連ではプロジェクトやプロダクトを作る際に、どのステークホルダーに相談をしたか、相談者のジェンダー・地域バランスは取れているかなど、あらゆる場面で平等性・包括性が求められます。一方で、プロジェクトを計画通りに進めるためには一定程度の牽引力も必要で、このバランスそのもの、またバランスの取り方(どうしたらスケジュールを守りつつ平等性・包括性が担保できるか)を意識しています。
現在は国連環境計画の持続可能なインフラ投資チームに所属し、官民が行うインフラ投資をSDGsやパリ目標に整合した持続可能なものにするための活動を行っています。具体的には、1.投資家が遵守するべき投資原則の作成・普及、2. 投資原則の国レベルの政策への反映支援、3. 官民資金の持続可能なインフラへの動員の3つの活動を中心的に行っています。
ワークライフバランスについてはしっかりと確保できていて、夜中まで仕事をしなければいけないことはほとんどありません。プライベートの時間はサッカー観戦、ゴルフ、ハイキング、スノーボード、サウナなどをしてリラックしています。ヨーロッパ、特にスイスは自然が豊かで、気分転換はしやすいかと思います。趣味以外では今後の就職、キャリアアップのためスキルアップに時間を使うことも多く、現在はフランス語の勉強や、オンラインで受けられる資格プログラムなどに参加しています。
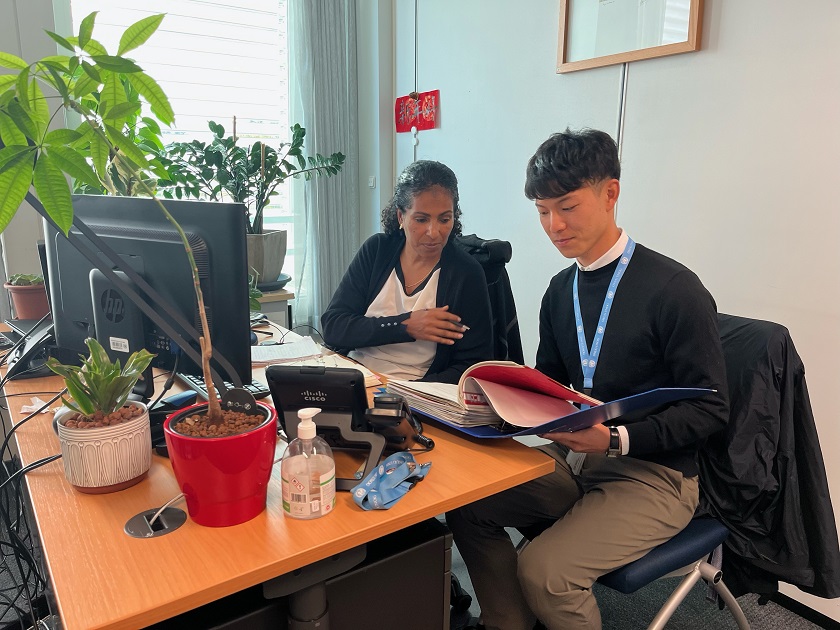
2022年 同僚とミーティング
中学、高校生時代は周りとあまり変わらない学生で、特に国際的な活動もしていませんでした。ただ授業の中では英語が一番得意で、周りに負けたくないと頑張っていた記憶はあります。いつか留学をしてみたいという漠然とした思いで大学は留学が卒業条件になっている学校を選び、そこで初めて海外に出ました。留学中は限られた期間でなるべく英語や現地の文化などを吸収するべく、積極的に周りの人とコミュニケーションを取るようにしました。上で述べたように帰国後に国際協力を志すようになったのですが、就職が決まった後に途上国(スリランカ)にボランティアに行くことを決めました。仕事として途上国に携わる前に、学生のうちに現場のコミュニティレベルでの生活を経験したいと思ったのがきっかけです。 学部卒業後直ぐに就職し、新卒の会社でちょうど3年間勤務し次の会社に転職するタイミングで大学院に行くことを決めました。大学院は国内の夜間MBAを選択したのですが、理由は、アカデミックな問題意識は実務から生まれると考え仕事を継続したかったことと、転職先でファイナンスの仕事をする予定だったので体系的に経営・財務・ファイナンスのことを学びたいと考えたからです。 学生時代にしておいて良かったことは、物事を構造立てて理解・発信する力を養うことです。専攻、専門分野を学習することはもちろん大切なのですが、それ以上に物事を体系的に理解し、アウトプットできる力を養うことが重要だと考えています。仕事で当然さまざまな文章を読み書きする機会がありますが、要点がまとまっていない文章に出会うことは多々あります。反対に自分が書く立場になった時はポイントごとに伝わりやすく書くことを第一に意識しています。仕事を始めてから構造化やライティングに関して体系的に学ぶ機会はあまりなく、また若い頃から取り組んでいた方がより自然と意識できると思いますので、学生時代の取り組みが今の財産になっていると感じています。
国際機関での仕事は2年から3年の任期があることが多く、常にこのサイクルで職探しをしなければなりません。一般的に職探しは各国際機関に空席が出たタイミングで随時応募をするのですが、一つのポジションに世界中から応募者が集まるため非常に競争率が高く、また書類の提出から最終的な業務開始まで長ければ一年程度かかることもあり、逆算するとかなり前から仕事探しをしなければなりません。国際機関で仕事をする立場として、職探しは常にプレッシャーで、また長期的な人生設計が難しい一つの要因であるとも思います。当然自身やパートナーのライフステージによって任地や職種を選ばなければならないタイミングもあり、自身が転職をしたい、しなければいけないタイミングで適正にあった、行きたい任地の仕事があるとは限りません。しかし、この2−3年のスパンをポジティブに捉えれば、常に自身のキャリアパス、やりたいことを考えるきっかけになり、またポジション確保に向けてスキルアップのモチベーションにもなります。 私自身現在ものこのスパンで仕事探しをしているのですが、転職先候補には国際機関職員以外に民間企業への就職も選択肢の一つとして持っています。これは上記のような仕事の安定というよりも、仕事内容の理由が大きいです。日本には優れた技術と資金力を有し積極的に海外進出をしている企業がたくさんあります。世界的にみても自国でこのような職場を見つけられる国はそう多くはないと思います。民間企業の高い期待値(質、成果、スピード)の中で仕事をすることは確実にスキルアップにつながりますし、このスキルはまた国際機関に戻ろうとするときにも役立つと思います。

2022年 オフィスにて
国際分野の仕事には専門性、言語力、海外での経験が必要という印象があるかと思います。どれも正しいのですが、この中で私が一番必要だと考えるのは専門性です。日本では国内と海外の仕事が切り分けて考えられがちですが、日本の知識、技術はどれも世界から見たときにも優れていることが多く、国内から海外に舞台を変更しようとする際にも必ずいかすことができます。若いうちから活躍できる国際分野の仕事が多くないのは事実だと思いますが、一方でこの時期に国内でたくさん学ぶことも重要で、その方が長期的に活躍もできるのではないかと思います。ただし海外で働くためには国内で取り扱う課題や技術をグローバルの視点に昇華し、地域、国の視点に当てはめていくことが必要で、日常からその問題意識を持っておくこと、または海外大学院等で学ぶことが有益だと思います。有難いことに日本政府は日本人の国際機関職員を増やすべくさまざまなプログラム(JPO等)を提供しており、しっかりと自身の専門性とそれが国際機関でどのようにいかせるのかを説明することができれば、国内から海外への舞台チェンジも可能だと思います。