
国際機関に興味をもったきっかけは大学生の時に参加した海外ワークキャンプでした。モンゴル、メキシコ、ケニアにそれぞれ3週間滞在し、現地住民や海外から集まった同年代の方たちと寝食を共にしながら、植林、ウミガメ保護、児童教育などのボランティアをしました。特にケニアでは、マラリアに感染し、マサイマラという都心から離れた大きな病院もない地域で、ほとんど治療手段がなかった中、WHOが薬を支援する小さな病院(小屋?)があり、一命を取り留めたことがありました。こうした経験から途上国で社会のために働く楽しさや、国際機関の重要性を知り、いつか働きたいと思いました。
しかし、大学卒業後すぐには国際機関を目指さず、まずは日本の専門商社に入りました。理由は1.国際機関は修士号があった方がよいのですが、借りていた奨学金の返済もあり経済的にすぐ大学院にはいけなかった、2.就職活動をしていくうちに、商社の仕事も途上国支援につながると思えた、3.国際機関は最低3年の職務経験が必要な場合が多く、どのみちいつか職務経験を積む必要があったからです。こうした理由から、まずは商社で働いてみて、国際機関の道へ進むかは3年後に改めて考えようと思っていました。商社ではアフリカとラテンアメリカ向けの建設機械の輸出や現地企業への販売戦略の支援などを担当し、面白い仕事でしたが、やはり国際機関にいきたい気持ちが強く、もっと社会貢献や地域の方々と協力して働きたいという思いから、会社を辞めてアメリカの大学院に進み、JPOを通じてILOに入りました。
JPOについては商社勤務の時からよく調べて準備をしていました。外務省国際機関人事センターのイベントになるべく参加し、応募条件や先輩の体験談など情報収集をしていました。アメリカの大学院では教授のコネなどを使い、世界銀行、IMF、国連本部の方などに会ってアドバイスを頂きました。ポイントは1.近い将来(3年後くらい)自分がどこでどんなポストにつきたいか具体的に想像して、そのために必要な経験や知識を集めていくことと2.国際機関で働く方になるべく会って話をきいて具体的イメージをもつことかと思います。これによって得られる知識や人脈はJPO選考でとても役に立つと思います。
JPO任期中の早い段階から上司には3年目以降もILOで働きたいという意志を伝えていました。資金の乏しい部署だったので、早めに意志を伝えることで、色々な可能性を検討する時間がとれたと思います。私の場合、ILO正規職員の予算(Regular Budget)を取るのは極めて難しい状況でしたので、代わりに日本のようなドナー政府の任意拠出金によるプロジェクト(Development Cooperation project)から自分の人件費を工面する方針で、自らファンドレイズの交渉をしたり、すでにプロジェクトを持っている同僚に相談をしました。その結果、JPOを3年目まで延長する予算は確保することができました。
上記の「契約延長」の交渉と並行して進めたのが、「新規ポストの獲得」に向けた活動です。空席公募にはJPO2年目から年間15ポストくらいは応募していました。その結果、ちょうどJPO3年目が終わるタイミングで、現在のベターワークプログラムのオファーを頂き、転籍(JPO卒業)をすることができました。但し、今のポストは待遇こそILO正規職員と同等ですが、プロジェクトに紐づくプロジェクト職員ですので、終身雇用というわけではありません。また2-3年後には自らポストを探さなければならないので、これから準備をしていくところです。
ベターワークプログラムはILOと世界銀行IFCが世界13カ国で展開する衣料品産業のサプライチェーン改善プログラムです。具体的には衣料品産業で働く労働者の権利や工場の生産性向上を目的としており、世界に約300名のスタッフがいます。私はファイナンス&プログラムオフィサーとして、2つの業務を担当しています。1.ファイナンス業務は各国のプロジェクトの資金が契約期間内にきちんと使われているかモニタリングし、アドバイスを行います。具体的には各カントリープログラムの年間資金計画の作成とレビュー、カントリープログラム間の資金の過不足調整、ドナー政府に提出する財務諸表の作成などです。2.プログラム業務ではドナー政府との資金調達の交渉や進行中のプロジェクトのモニタリング評価を担当しています。各プロジェクトには達成すべき目標や具体的な活動計画があるので、カントリープログラムのスタッフと達成状況や計画の進捗を確認し、ドナー政府に報告します。出張は年に3-4回程度あります。
 2023年 衣料品ブランド企業向けのサステナビリティに関するワークショップの様子
2023年 衣料品ブランド企業向けのサステナビリティに関するワークショップの様子
国際機関に勤め続けるには「専門性」が必要とよく言われます。ILOの中だと、例えば中小企業、多国籍企業、雇用、スキル開発、労働者保護、社会保障、児童労働、ジェンダーなどのテーマの専門性や、人事、会計、ITなどのバックオフィスの専門性などがあります。こうしたスペシャリストのポストがILOでは大半を占めますが、中にはマネジメントとして全体をみるジェネラリストのポストも存在します。各国のカントリーダイレクターやプログラムマネージャーと呼ばれる人たちです。私の現在のポストもどちらかというとジェネラリストにあたります。ただ、そうしたポストでも何らかの専門性、自分の得意分野は持っておいた方がいいです。私の場合は商社でのビジネス経験やJPOで中小企業支援、若者の起業家育成を担当してきたことから中小企業開発、起業家精神開発を専門としています。こうした専門性はいまのベターワークでも活かせています。

大学生の時から海外ワークキャンプや海外留学をして、異文化交流経験を積むのはやっておいてよかったと思います。留学は大学2年生の時にアメリカ、イリノイ州のマンモス大学という小さなリベラルアーツカレッジに1年間交換留学に行きました。初めて親元を離れて、アメリカ人のルームメイトと生活を共にしました。日本人留学生は5人しかいない大学で、多くの時間をアメリカ人や他国からの留学生と過ごし、政治、文化、食事、言語など様々なことを知りました。国連はまさに人種のるつぼです。様々な民族、国籍のスタッフと腹を割って人間関係を作るにはそれぞれの国の政治や文化を理解することが重要です。簡単な例でいえば、イスラム圏の同僚とランチに行くのに豚肉料理が美味しいお店を選んだら100%嫌がられます。ロシア人とウクライナ人の同僚と同じエレベーターに乗ったら会話には気を遣います。このご時世なので政治的な話は避けて、料理や天気の話をします。こうした感覚は大学時代の異文化交流経験で培われたと思います。
留学にはとてもお金がかかりました。私は大学時代の交換留学1年と、大学院でアメリカに2年いて一番苦労したのがお金の工面でした。ただ、貯金がなくても、両親を頼れなくても、道はあります。大学院はジョージワシントン大学のエリオットスクールというところで、2年間で学費と生活費合わせて約1600万円かかりました。私の場合ほとんど貯金もなく、両親も頼れなかったのですが、5割を給付型奨学金、3割を貸与型奨学金、2割をアルバイトと貯金でまかなうことでなんとかなりました。大切なことは2-3年前から奨学金の募集要項をよく読んで計画的に準備すること、応募書類をいろんな人に読んでもらいアドバイスをもらうことだと思います。給付型奨学金は一部の超優秀な人しかもらえないと思われがちですが、ぜひ色々と調べてみてください。実は倍率が低いものや、応募条件がやさしいものも沢山あります。日本は大学院(特に文系)に行く人が少ないので、チャンスは実は多いと個人的には感じました。また、人に相談することで自分のやりたいことがよりクリアになり、応募書類も洗練されていきます。お金の問題はもちろん大きな壁ですが、必ず乗り越える術があると思います。ぜひ金銭面を理由に諦めず、まずはトライしてほしいと思います!
私の現在のポストは特定のプロジェクトに紐付くDevelopment Cooperation staff(DC staff)という種類のポストで任期があります。そのプロジェクトの契約期間が終わると私の人件費を払うことはできなくなりますので、ファンドレイズをしてプロジェクトを継続するか、新しいポストを探さなければなりません。簡単に言えば2-3年に一度就活をするような感覚です。私は日本の商社で正社員として働いていたので、終身雇用の安定感を知っています。会社を辞める時、本当に今の自分に他の仕事ができるのだろうか、国連に行けるのかという不安はありました。またJPOの後半にはなかなか次のポストが決まらず、契約終了が迫ってくるプレッシャー、妻と子どもはどうなるのかという不安もありました。でも、なんとかなります。大切なのは1) 2-3年後を見据えて計画的に動くこと、2) キャリアについて相談できる同僚をたくさん持つこと、3) プランBやプランCを持っておくことだと思います。私の場合、Plan BはJICA専門調査員や国連のコンサルタント、日系国際開発コンサル会社など、Plan Cは日本の民間企業や国際NGOなどでした。
私には妻と1歳の息子がいます。バンコクは学校や病院、大型ショッピングモールも沢山あるので子育てには全く問題ないですが、いつかはもっと途上国で働きたいと思っています。大切なことはキャリアのことをオープンに話して、家族の理解を得ることだと思います。JPO後半で色々な空席公募に応募している時、妻にはどこのポストに応募していて、受かったらどうするかという話を常にしていました。バンコク以外にもイラン、バヌアツの選考が進んでいましたが、妻とよく話し合った結果、バンコクのオファーを受けることにしました。国連スタッフは仕事の性質上、家族が一緒にいられないこともあります。やむを得ず夫婦別居をする方もいますし、それが嫌で国連を離れる人もいます。私の場合は、なるべく家族が一緒にいられるポストを選びますが、もしどうしても家族帯同不可の国しか選択肢がなくなった場合は、1-2年など期間を絞り、頻繁に家族に会いに行くなどすれば乗り切れるかなとも思っています。
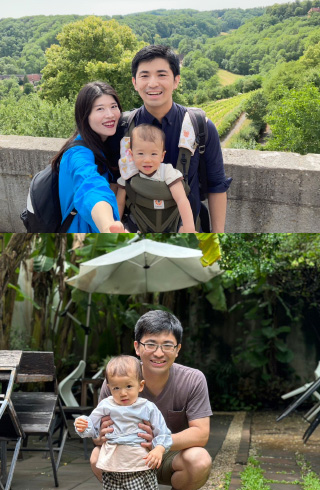
私は20代前半の大学生のころから、途上国でのワークキャンプ活動をきっかけに国連に関心を持ち始めました。真剣にキャリアとして考え、準備を開始したのは24歳くらいの時です。学生のうちは異文化交流に力を入れることをおすすめします。海外大学に進学したり、交換留学に行くのがベストですが、それが難しければ、日本でも様々な交流イベントがありますし、学校にも留学生はいると思います。外国の友人をたくさん作って、彼らの国のことをよく知ってください。国際分野のキャリアに進むには2-3年後を見据えて計画を練り、自分に足りないものを補っていくことが大事だと思います。国連の求人情報は公表されており、外務省国際機関人事センターのHPで空席ポスト一覧や募集要項(Job Description)をみることができます。その中から興味のある国際機関やポストを絞り込み、募集要項を読んでいくと、自分に必要な学歴、職務経験、言語能力などが分かります。今すぐに国連で働けるわけでなくても、ポスト情報は役に立ちます。今も数年後も掲載されるポストや必要条件が大幅に変わることは考えにくいからです。まずは自分の専門分野を定めて、行きたい国際機関を3つくらいに絞ることをおすすめします。決めきれないかもしれませんが、選択と集中はとても大切です。あと、正直なところそれが人生の最終決断ではありませんのであまり気負いすぎないで下さい。もしかしたら20年後は少し違う専門分野になっているかも知れませんが、今は2-3年先を考えている、その間に自分はどんな専門分野を追究したいかを考えてください。専門分野は変わることがあると思いますが、よく考えて行動すれば大筋がそれることはないと思います。
ぜひ視野を広く持って、日本を飛び出して、いろんなことにチャレンジしてみてください!