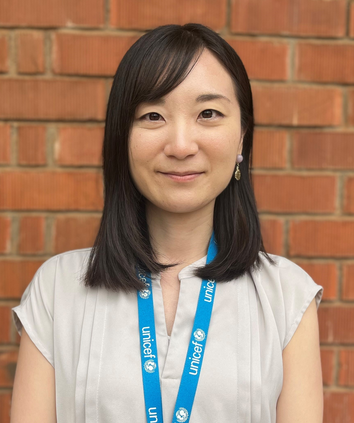
学生時代から途上国の貧困、児童労働や教育問題などに関心があり、大学では国際関係を専攻していましたが、学部卒業時点のビジョンは「世界を舞台に現地の人々と協業して社会にポジティブな影響を生み出す仕事をしたい」というもので、国際機関を目指すような意識は特段持っておらず、まずはグローバルに働けそうな組織を探して、民間企業に就職しました。しかし2015~16年頃、日々悪化するシリア内戦に気を揉み、また東南アジアで社会経済的に困難な状況に置かれた子どもたちを目の当たりにするなかで、そのような社会的不平等や不正義の解決に直接関与したい、自分の人生の大半を占める仕事は子どもたちの未来を少しでも明るくするものにしたいと思うようになりました。特に、2017年夏にガーナの現地NGOにてインターンをした際、児童労働問題一つをとっても、本質的な問題解決には、政策レベルと事業実施レベル双方で複数セクターにまたがった支援が必要であると理解したこと、またより多くの子どもやユースの学びと成長を支援したいと思っていたことから、そのようなアプローチが可能な国際機関、そして教育やスキル育成分野でリードをしているUNICEFに興味を持ちました。
翌年に英国大学院を卒業後、UNICEFヨルダン事務所でインターンを行ったのち、外務省の平和構築人材育成事業を通じて同インドネシア事務所にてUNVとして勤務しました 。その後、日本のODAのあり方や仕組みを知りたくJICAに転職しましたが、誰のために、どのように働きたいのかを考える機会にもなり、「すべての子どもの権利を実現する」というUNICEFのマンデートに改めて強く共感するとともに、自らの関心分野における専門性をさらに高めたいという想いから、JPO派遣制度を利用して2022年春よりUNICEFウガンダ事務所にて勤務をしています。
本制度への応募にあたっては、読み手の心に訴える、分かりやすい書類の作りこみに時間をかけました。国際機関での勤務を学生時代から意識して就職した周囲の人々と比べると、私は応募時点で開発業界における経験年数は多くありませんでしたが、UNICEFの国事務所でのインターンやUNVを通じて、少なからず希望ポストで求められる知見と経験を持っていること、またいかにJICAや民間企業での経験が生きるかということを工夫して伝えるようにしました。
まず最初に、ウガンダの10代の子どもたちの教育事情について簡単に触れたいと思います。ウガンダでは子どもたちのドロップアウトや不就学が深刻な問題となっており、2015~16年時点で、12歳以上も含む初等教育修了率は50%ほど、そして13~16歳のうちの40%以上、17~18歳のうちの70%以上が学校教育を受けられていないという危機的な状況にありました。その背景には、学校の環境や先生の質の問題のほか、隣国からの度重なる難民流入による生徒数の急増とそれに起因する授業の質の低下、各家庭の経済状況、地域社会の伝統的価値観、そして様々な理由により15~19歳の女の子の四人に一人が早すぎる妊娠・出産をしていることなど複合的な要因が重なり合っています。そして、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、2022年春まで世界最長の2年間の学校閉鎖が行われたことによりその状況はさらに悪化し、今も多くの子どもたちが学校に通えず、知識やスキルを得る機会をなく、社会経済的に困難しながら日々を生きている状況です。 すべての子どもたちが質の高い学校教育にアクセスできることが一番なので、私の所属する教育セクションでは、質の高いインクルーシブな教育の提供に必要な各種支援を行いつつ、並行して10代の不就学児を対象とした21世紀型スキル育成(ライフスキル、デジタルスキル、ソーシャルイノベーション・アントレプレナーシップスキルを育むノンフォーマル教育)事業、また各地域の行政が子どもに優しいものとなるよう、子どもたちの声を取り込むために政府とともに立ち上げた子ども代表団などを中心とした社会参画事業を実施しています。私は21世紀型スキルの中でもソーシャルイノベーション・社会起業家精神育成を主眼とした事業(UPSHIFT)、また、同事業を卒業した子どもやユースをその先の雇用機会につなげるための施策の立案・実施、そして子ども代表団の支援に主に取り組んでいますが、ここではUPSHIFTに焦点を当ててお話ししたいと思います。
UPSHIFTは現在世界40か国以上で展開されているカリキュラムであり、問題解決能力、批判的思考力、創造力、チームワーク、自己肯定感など、様々な分野で通用する能力やスキルを育むもので、自分たちの住む地域の課題と原因分析をし、それに対する新たな解決策を考え、行動を起こせる人材を育てるものです。ウガンダでは、学校教育を受けられていない子どもたちやユースに対してオルタナティブな学びと自立の機会を提供すること、そして地域社会にイノベーションを起こすことを第一の目的として、国際労働機関(ILO)と連携をしながら事業を推進しています。カリキュラムの認可、実施拠点の選別・強化、実施主体(政府)の能力強化およびアセスメントの仕組みづくりと実施を並行して行い、そのエビデンスをもとに中長期的にはウガンダ政府の21世紀型スキル育成分野に関する政策や計画の意思決定に影響を与え、UNICEFの支援の手を離れても同分野の支援がウガンダの教育セクターで継続されるよう画策しています。既存のシステムにはない仕組みを作ろうとするこのような取り組みこそ、その維持、拡大を可能にするためには、初期段階から戦略的に政府をはじめとしたステークホルダーを巻き込むことが大切であり、なかなか時間はかかりますが、このようなスケールの仕事ができることがUNICEFの仕事の醍醐味だと感じます。

2023年2月、中央部のエンテベにて、会議の合間にILOのカウンターパートと打ち合わせ
© UNICEF/Uganda/2023/Tsunokake
これまでに直面した困難なエピソードの一つとしては、まだJPOとして着任してから日も浅くUPSHIFTカリキュラムの理解も十分ではなかった頃、同カリキュラムのメンター候補のユース40人に対する5日間のトレーニングを北部カラモジャ地域で実施することになりました。このトレーニングの質が同地域における本事業の質そのものに直結するものであったため、カリキュラムを熟知する上司と二人で出張して実施する予定だったのですが、前日に上司が体調不良となり急に一緒に行くことができなくなりました。自分一人で実施することに大変な不安を覚えましたが、日程変更は不可能だったため、事前に決めていた上司のパートを自分でカバーできるよう道中に勉強し、トレーニング実施を支援していたパートナーNGOの中にカリキュラムの知識を多少持っているスタッフがいたため協力を仰ぎ急遽講師チームを編成。毎朝事前ブリーフをしながらチームとして対応し、どうしても上司のサポートが必要な部分は、当日オンラインで上司をつなぎリアルタイムでアドバイスを貰うなどの臨機応変な対応を試み、なんとか乗り切ることができました。直前の予定変更と精神的によりどころのない中でこの出張は非常にタフなものでしたが、臨機応変に対応し、できる限りのことをやりつくしたことで様々な面で自信を持つことができました。

2023年4月、北部のカラモジャ地域にて、UPSHIFTに参加する子どもたち、メンター、NGOパートナーと
© UNICEF/Uganda/2022/Tsunokake
UNICEF職員の仕事は、政府の政策・制度作りや能力強化、およびNGO等とのパートナーシップを通じた事業展開が主であり、自ら全国各地に赴いてメンターを育てるためのトレーニングを実施することは多くないかと思います。これは、この分野のスペシャリストになるには自らカリキュラムを熟知すべきだという上司の考えのもと取り組んでいるものですが、そのプロセスを通じて、事業を本質的に理解しリードしているという自負を得ているため、当初は苦しい場面も多かったですが、軌道に乗ってきた今は非常にありがたく思います。 私は日本の民間企業からキャリアをスタートしましたが、企業にとっての経営資源である情報の分析、そして人材・モノ・資金を動かす経験を様々させていただきました。その中で得た課題分析・実行力、人間関係構築力、コミュニケーション力などは、UNICEFで働くうえでも役立っていると思います。もちろん異なるバックグラウンドの人々と外国語を使用して協働するなかでは、それらのスキルを100%のクオリティで発揮することは難しかったりもしますが、今ここで働くうえでの基礎体力になっていると思います。

2023年2月、中央部のエンテベにて、UNICEFのパートナーNGOへトレーニングする様子
© UNICEF/Uganda/2023/Tsunokake
幼稚園の頃、父親の仕事の都合で2年ほどアメリカに住んでいたことがあったため、物心ついたころから海外への強い関心をずっと抱いていましたが、中高時代は習い事や部活、勉強などで忙しく、その機会なく過ごしていました。大学進学後、途上国の貧困、児童労働や教育問題などに関心はありつつも、まずは英語力を磨きたいと思っていたため、2年次に語学留学、3年次には米国へ1年間交換留学し、現地では日々勉学に励むとともに、地域に根差したボランティア活動や、現地NPOの国際交流・教育事業のインターンにも取り組みました。また、大学卒業前には、内閣府青年国際交流事業に参加し、世界10か国から集結した200人以上の同世代の若者たちとともに船上での共同生活を送り、南アジア地域を訪問する経験などもしました。今振り返ると、このように異文化や新しい環境に積極的に飛び込み、バックグラウンドの異なる人々と協働する機会を数多く経験するなかで、今の仕事につながる語学力、異文化適応力やコミュニケーション力が自然と身についたように思います。一度就職すると時間の制約もありこのような機会を数多く得ることが難しくなるので、学生時代に経験できて良かったと思います。
前述の通り、民間企業での勤務を経てから、サセックス大学の開発学研究所(IDS)へ大学院留学をしました。この進学先を選んだ理由は、開発学において国際的に高い評価を得ている研究機関であること、開発分野に関連する職歴があることが基本的な入学条件で、先生たちも第一線で活躍する現役の研究者たちであることから最先端の知識をもつ先生や様々な現場経験を持つ仲間に人々に囲まれて勉学に励むことができること、またロンドンより家賃や生活費が安く抑えられる南部の町ブライトンにあるということなどが挙げられます。IDSでの一年間は本当にあっという間でしたが、多くの仲間と出会い、学びあい、その後のキャリアにつながる礎を築くことができました。
大学院卒業後は、日本ユニセフ協会の国際協力人材養成プログラムを通じて、UNICEFヨルダン事務所でインターンをする機会をいただきました。大学院留学を決めたときから卒業後のキャリア開拓の機会として同プログラムに関心を持っていたため、大学院に進学してすぐに応募をしました。幸運にも合格することができ、大学院での研究内容の関係からシリア周辺国を希望として提出したところ、結果としてヨルダン事務所へ派遣いただきました 。
私のように日本の教育および雇用制度のもとで育ち、生きてきた人にとっては特に、契約形態や文化が全く異なる国際機関での勤務を継続することは、精神的に決して楽ではないと感じます。日本の民間企業では、外資系企業をはじめとして徐々に変化してはいるものの、終身雇用制度や年功序列モデルが実態としてまだ色濃く残る中、国際機関では完全成果主義、かつ運とご縁も十二分に味方につけて常に就職活動を行うバイタリティが必要とされています。
キャリア選択への考え方は人それぞれですが、個人的には自身が情熱を持つ世界の開発課題の解決に貢献する形は様々あるはずだと思っています。JPO後は、専門性を生かして国際機関内でポストを獲得することがもちろん期待されていますが、長い職業人生においては、例えば自らの知識をアップデートするべく大学院で学び直す、経験と視野を多様化・多角化するべく自分の専門分野においてリードしている他のアクターで働く、そこで責任あるトップマネジメントの経験を積むなど、様々な選択肢があってよいはずで、それらの経験を経て身に着けた知識やスキルが、結果として国際機関で新たに上のポストを獲得し活躍する礎になることもあるのだろうと思っています。
先輩職員の方々のお話を聞いたり、また今の自身の経験を通じて感じるのは、パートナーのキャリア問題、家族同伴の調整、子どもが生まれ家族が増えた際の仕事と家庭のバランスのとり方など、数年の有期契約を前提とした国際的な移動が求められる職業であるがゆえに、乗り越えなければならない課題が常にあるということです。ありきたりの言葉ではありますが、キャリア構築においては、自分のやりたいことや大切なものに噓をつかず、一方で、どの選択が短期的、また中・長期的に自分や家族にとって有益かをその時々で考えながら、最善の挑戦と選択を重ねていきたいと思っています。
国際協力でのキャリア構築に関心がある学生さんは、まずは自らの関心分野に沿うボランティアやインターンシップなどの機会を探して、ぜひ小さな一歩を踏み出してみてほしいです。具体的にどのようなことをやっていいかわからない、自信がないと思うことも多いかと思いますが、自分が憧れる何かをすでに実現している人に勇気を出して話を聞きに行きアドバイスをもらうのが、自己実現のための道を模索するうえで一番効果的だと思います。また、語学力と異文化コミュニケーション力の獲得は、学生のうちに様々な機会を活用してぜひ積極的に行うとよいと思います。
すでに社会人で、今は国際協力とは直接関係のない仕事をしているものの、国際協力を仕事とすることに関心が高まってきたという方も、ぜひ同じように自分の目指したい姿をすでに実現している人々にたくさん話を聞き、情報収集をたくさん行っていただくとよいと思います。特に国際機関で働いている方々は一人ひとり異なるキャリアパスをたどっており十人十色だと感じるので、ぜひ、ご自身だけのユニークな人生デザインを楽しんでいただけたらと思います。多くの場合が有期雇用前提で、常に自分の知識や経験のアップデートを図りながら転職活動をつづけていく必要があるので楽ではないかもしれませんが、初心を忘れずに精進し、かつその状態を楽しめていれば道は開けてくると私も信じていますので、みんなで頑張っていきましょう。

2023年2月、首都カンパラにて、教育セクションの年次計画作成会議での集合写真
© UNICEF/Uganda/2023/Tsunokake