
大学4年生の時に、たまたま大学で実施された国際機関キャリアセミナー(外務省主催)に出席したことがきっかけで、国際協力やJPO派遣制度に興味を持ちました。漠然と憧れを抱いたものの、当時は国際機関という選択肢があること自体初耳でしたし、英語もほとんど話せなかったため、まずは交換留学、カリブ海での国際協力インターンと経験を積むことで、自分の興味が本物と確信し、国際協力の世界に足を踏み入れました。
自分が培った専門性や技術、ソフトスキルを、最大限活用しながら、より多くの影響力をもって社会に貢献するためには、企業利益や国益に制限されない環境で、理念実現のために働くことができる、国際機関が最適だと考えました。
UNFCCC事務局は、世界規模での気候変動対策関連の仕組み作り等を話し合う、国際交渉を支援する機関です。国際交渉の現場から、リアルタイムに支援できることに魅力を感じたことと、求められる職務内容と今までの経験の合致度が高く、専門性を最も活かすことができるのはこの機関だと確信し、UNFCCC事務局を志望しました。
民間からの転職が珍しい世界なので、民間出身というだけで、自然と民間投資や気候資金関係の分析を任せてもらえ、他の気候変動の専門家たちと差別化するための個性として、役立ちました。
また、民間にいた当時、議事録やメールの文案は上司から真っ赤に修正されましたが、国際機関では即戦力として雇われているため、そのようなフィードバックもないことが多いです。民間で、任務遂行に関わる基礎的な能力を磨く機会をいただいたことは、今でも役立っていますし、感謝していることでもあります。
国際機関で働いている知り合いが全くいなかったため、実際の仕事内容やキャリアパス、JPOの先輩方はどのような試験対策をされたのか知るために、JPO試験対策講座や、LinkedInを通じて人脈構築や情報収集に励みました。そうした活動を通じて、応募を応援してくださるメンターや、先輩方、同じく国際公務員を志す方々に出会えたことで、様々な視点からアドバイスいただき、応募書類作成から派遣されるまでの長い年月を走り切ることができたと思います。
後発開発途上国(LDCs)の気候資金へのアクセス状況の分析や、気候変動適応策の実施状況の評価、LDCs専門家会議の開催とインプット作成の支援、COPでの国際交渉や関連イベントの支援、LDCs各国との対話を通じた適応策策定と実施の進捗確認・評価、地域別ワークショップの開催を通じたLDCsのキャパシティビルディング、Expo開催の支援等
特に国際交渉の場では、事務局として円滑かつ公平な会議運営が求められるので、議論が白熱している時こそ感情が表情に出ないようグッと堪えて、不必要な誤解をまねくことがないよう、より丁寧で婉曲的な表現で、コミュニケーションするよう心がけています。

COP27でのイベント運営支援の様子
今の業務では、西アフリカの国々との会議でフランス語が使用されることも多いため、フランス語を日本語で教わることができた間に、少しでも準備しておけたら良かったな、と思います。
多様なバックグラウンドをもち、ワークライフバランスを大切にしている方々に囲まれているので、周りからの家族やプライベートな事情への理解や配慮が高く、あまり自分で意識的に取り組まずとも、自然とワークライフバランスを保つことができるように思います。
より効率的にデータ分析するためにも、プログラミング言語やデータ分析ソフトの習得、より活躍の場を広げるためにも、フランス語のスキルアップを目指しています。
英語能力が高くて損をすることはないため、積極的に能力向上に努めつつ、西アフリカ地域等での業務も視野にいれる場合は、フランス語の習得も必要になってくるかと思います。 英語の習得方法に関しては、大学4年生にして、キャリアセミナーをきっかけに国際協力への興味をもったため、まずは忘れかけていた基礎文法からやり直し、受験もしやすいTOEICのスコアアップを通じてリーディングやリスニングの能力向上に努めました。その後は交換留学への応募をきっかけに、よりアカデミックなTOEFLやIELTSでのスコアアップを通じて、留学最低レベルの英語能力は確保し、その後の留学先でのディスカッションやレポート作成、就職先での英語会議やメールでのやり取り等を経て、何年もかけてようやく習得しました。言語は学びに終わりがないため、今も勉強中です。
国際協力に興味をもち、留学やインターンを通じて国際協力の現場に積極的に関わっていたことは、その後の就職活動を有利に進める上で役立っていたと思います。特に、JPO応募時点で専門性を確立するためには、新卒採用先での業務内容が非常に重要になってくるので、戦略的に就職先を選び、途上国業務での即戦力として認められるよう、学生時代に語学の向上や途上国支援に携わっていて良かったな、と思います。
JICAインターンとして、JICA専門家の方の指導の下、カリブ海地域での持続可能な水産資源管理に携わっていました。二国間援助を通じた国際協力を専門家の方から直に学ぶことができ、その後の多国間援助への関心を高めるきっかけともなった、非常に貴重な途上国インターン経験だったと思います。

COP27でのイベントのモデレーションを確認している様子
気候変動による海洋酸性化やその対策に興味があったので、水産学を学ぶことができる国内大学に進学しました。大学院では、水産学だけでなく、気候変動や環境保全として専門性を広げたかったことと、既に交換留学に内定していたこともあり、同大学の気候変動に特化した大学院に進学しました。
その後社会人経験を経て、気候変動と民間資金に興味が移り、世界トップレベルの環境で包括的にビジネスを学びたかったことと、気候変動に加えてプロジェクトマネジメントの専門家としても専門性を解釈できるよう、英国大学院にMBA留学しました。
いずれの選択でも、興味関心の赴くまま、時代のニーズに合わせて、専門性の幅を広げようとした結果が、国際機関での就職に結びついたのではないかと思います。
JPOとしての任期が決まっていることで、日々の業務に加えて正規ポスト獲得に努めなければいけないことは、中々落ち着かないと感じることもあります。ただ、JPO派遣前と派遣後(現在)では、書類選考の突破率が全く違いますし、今の経験のおかげで応募要件を満たす公募の数も増え、確実に自分の目指したいキャリアに向かって前進していると感じるため、任期付きで派遣されることは、必ずしもネガティブなことではないと思っています。
今現在、気候変動関連の正規ポスト獲得に向けて職探し中ですが、今までの職務内容と合致するようなポストは、自分の興味関心と一致するポストでもありますし、そういったポスト応募に向けて研究や分析をすることで、より自分の専門性が深まるきっかけにもなっているので、むしろこの機会を自己実現のためのチャンスと捉えて、前向きに取り組んでいます。

カンボジアのワークショップでの集合写真
日本の終身雇用制度とは一線を画す雇用形態とは思いますが、自分の進みたい方向に向かってずっと挑戦し続けることができ、周囲もそれを当然と受け止めてくれる環境で勤務することは、やりがいや情熱を持ち続けながら仕事をすることに繋がっていると思います。
プランAからZまでもっておくこと、と先輩から教わったことがありますが、まさにその通りで、公募もどのタイミングでやってくるかわからないなか、あらゆるライフステージでの様々なキャリアでの選択肢を用意しつつ、臨機応変に対応していくことが大切だと思っています。
今は特に検討していませんが、もし今後、博士課程進学がほぼ必須のような状態になることがあれば、その際はポスト獲得のための進学も視野に入ってくるかと思います。
大学のGPAや語学の習得が、今後の大学院や留学等の進路選択、奨学金の有無にも響いてくるので、きっちり勉強して、自分の未来の選択肢を増やすようにすると良いかと思います。学生である特権を活かし、インターンに積極的に挑戦してみてください。
20代の職務内容がその後の専門性の方向性に大きく関わってくるので、どういった専門性をもちたいのか、修士号との関連性はあるか、その専門性を活かせる機関やポストはどこか、そのポスト獲得に途上国経験は必要か、色々と考えながら、キャリア構築することが大切だと思います。
UNVやJPO等への応募が現実味を帯びてくる一方、様々なライフイベントも重なってくる時期だと思うので、臨機応変に対応しつつも、自分の信念を大切に、自信がなくとも、まずは応募してみてください。
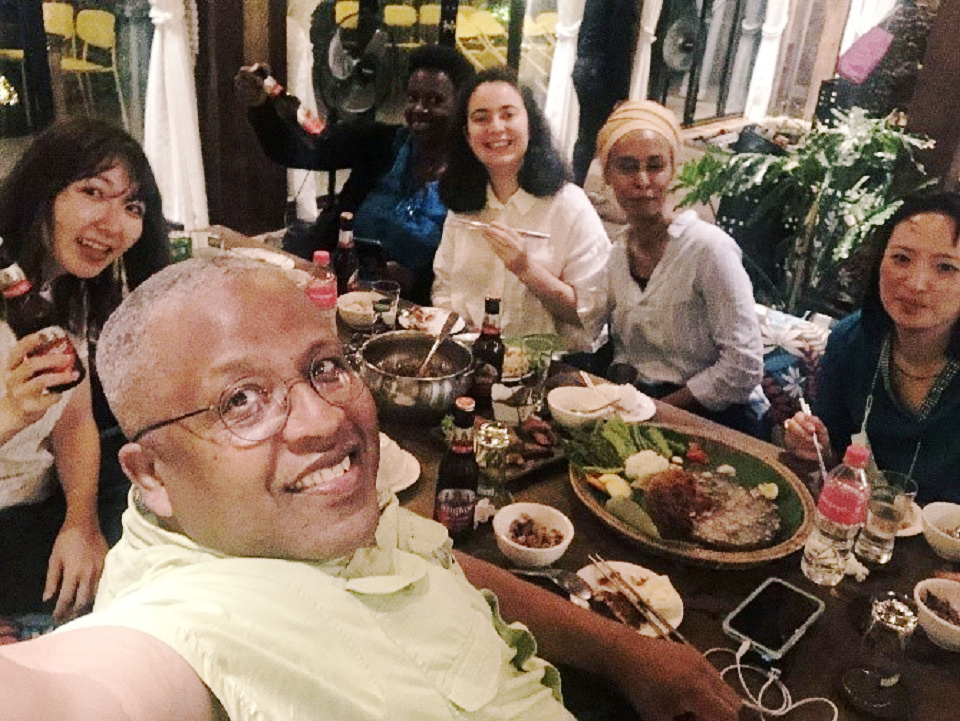
チームメンバーでの食事風景
自分の興味関心や、他人と比べて得意、不得意なこと等、自分をよく知ることが大切かと思います。どんな学部にいこうと、必ず必要とされるポストがあるのが国連機関なので、迷わず自分の興味に従ってください。また、この時期に外国語のスピーキングやライティングでのアウトプットにも慣れておくと、その後の語学習得が楽になるので、余力があればぜひ取り組むようにしてください。
とはいえ、10代にして国際機関を目指されているなんて、既に視野も広いと思いますし、とても素敵なことだと思うので、そこは大いに自信をもって、その情熱のままに突き進んでください。