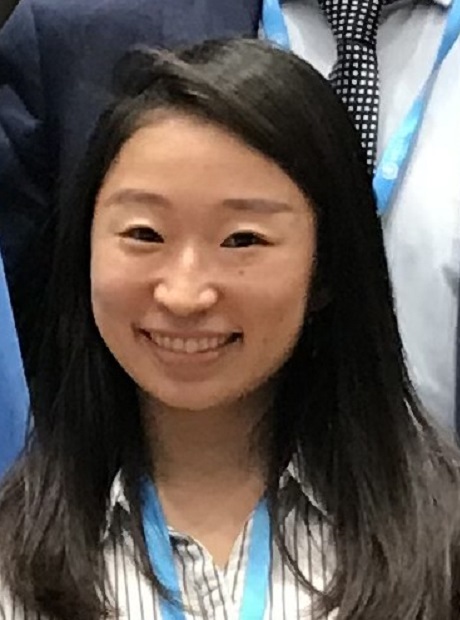
大学生の頃、東南アジアやアフリカでボランティア活動に携わる機会を多く頂きました。日本では国民皆保険制度に歯科治療も含まれており、誰でも必要な歯科疾患の予防や診療を受診することが基本的には可能である一方、諸外国ではこれが当たり前でないことを目の当たりにしました。また、多くのNGOや国連の活動は、エイズ・結核・マラリアなど命に直結する病気に関する活動をしており、口腔保健に関する活動は十分に行われていないことを知りました。WHOに口腔保健部門があることを知り、WHOでの勤務に興味を持つようになりました。
国際機関の中で自分の専門とする口腔衛生に関する業務を行うのはWHOしかないため、WHOでの勤務を希望しました。
1年目は書類審査に進めなかったので、2年目の応募時は時間をかけて応募書類を準備しました。
WHO本部では、Global Strategy on Oral Health(世界口腔保健戦略)やGlobal Oral Health Action Plan(世界口腔保健行動計画)、Global Oral Health Status Report(世界口腔保健レポート)の作成に携わっています。また加盟国への技術支援も行っており、保健省の歯科担当官と共に歯科政策の立案や、政策の実施を国事務所と連携して行なっております。
日本人は特に年齢よりも若く見られることが多いと思いますが、これは国際機関で働くうえでマイナスに働くことが多いと感じます。前回、キャリア相談をした方から、声を低く、語尾を上げずに話すといいと教えて頂き、実践を試みています。

2021年 世界口腔保健レポート発刊に際して
様々な国を訪問した経験から、多文化・異文化の中に溶け込むことが得意です。苦労もしましたが、友人や同僚僚との良い関係構築は、仕事の成果にも良く影響すると思います。
上司も他の同僚もワークライフバランスを保ち、ほぼ定時で仕事を終え休暇も取得しているのを見て、私も見習っています。週末にはメールを送らないように、有給中にメールの返事はしないようにとの指示を受けたことは新鮮でした。
週に二回フランス語講座を受けており、語学力向上に努めています。フランス語圏に住んでいるものの、仕事も日常生活もすべて英語のため、フランス語の上達にかなり苦労しています。また、健康の面からも週に二回ランニングをしており、昨年はジュネーブハーフマラソンを完走しました。今年はフルマラソンに挑戦したいです
発展途上国の現場を多く訪問しました。
大学3年生時に、JICA(国際協力機構)フィールドスタディープログラムの一環で、ラオスの農村部で健康保健調査をする機会があり、私も口腔保健調査に参加させて頂きました。村人が歯磨きの道具として、木の枝、蛇の皮のクリーム、ビンロウの葉を見せてくれました。アジアでビンロウの葉をタバコと混ぜて噛む習慣がある国があり、それは口腔癌のリスク因子であると大学で学んだ直後であったため、ビンロウの葉が歯磨きとして使用されていること、また日本では見ることのない木と蛇の皮のクリームで歯磨きが行われていることに衝撃を受けました。歯ブラシや歯磨き粉が買えない人々がいること、買える状況にあっても伝統的な手法での歯磨きを好むこと、フッ素の入った歯磨き粉の重要性が認知されていないことを目の当たりにし、正しい口腔保健教育の普及、保健システムの強化の重要性を感じました。
また大学6年生時に、NGOのインターンとしてマラウイで活動させて頂きました。現地の中学校で、口腔保健教育を企画・実行しました。「歯を健康に保つために何をしていますか?」という質問に対し、帰ってきた答えは「コカ・コーラのビンを栓抜きでなく歯で開けて運動をしている」というものでした。基本的な口腔衛生教育が実施されておらず、口腔保健教育を学校保健教育の一環として含まれる必要を認識しました。

2013年 ラオスでの口腔保健調査にて

2016年マラウィでの口腔保健教育にて
大学6年生の際に、現在勤務するWHO本部口腔保健部門にてインターンをしました。また大学院卒業後にヨルダンにある国連パレスチナ難民救済事業の保健部門でもインターンをさせて頂きました。異なる組織での経験はとても新鮮で、国際機関の行う多様な業務内容を学びました。
途上国の保健分野で世界を牽引するロンドン大学衛生熱帯医学大学院への進学を決意しました。公衆衛生修士課程には300人近い同級生がおり、様々な国の学生が世界の健康の推進に向けて一堂に勉強をする充実した学生生活を送りました。ほとんどの学生が医療のバックグランドをもっており、医師・看護師・獣医師・臨床検査技師など様々な人がいる中で、私が唯一の歯科医師でした。公衆衛生を目指す歯科医師が少ないことを目の当たりにし、途上国の口腔保健を推進する歯科医師になろうと決意しました。
大学院の進学にあたり、伊藤国際交流財団から奨学金を頂きました。この奨学金がなければ進学は実現しなかったため心から感謝しております。
探していますが、自分の専門性に特徴があるため、なかなか合うポストに出会うことがないのが難点です。
困難な部分も多くありますが、有給が多いことが気に入っています。また、上司も数週間単位で休暇を取得するので、私も遠慮せずに日本への一時帰国ができることがいい点かと思います。
もちろん継続した国際機関での勤務を希望していますが、空席がなければ難しいため、他の選択肢も視野にいれる必要があるのかもしれません。

2018年 ロンドン大学衛生熱低医学大学院修士課程にて
機会があるのであれば、是非、20代のうちに多くの挑戦をして国際分野でのキャリアを目指す方が増えると嬉しいです。海外大学院進学への奨学金なども、20代の方を対象としているものがおおいため、大いにチャンスのある年代だと思います。
大学生のころに多くの国を訪問し、自分の眼で見て感じた経験は一生の財産だと感じています。ぜひ、目の前の学問のみならず、多くのことにチャレンジして頂きたいです。