外務省国際機関人事センター Newsletter
第13弾
小池絵未の国際機関探訪


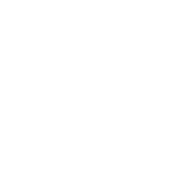 岡本カミンスキ健 さん
岡本カミンスキ健 さん
国連開発計画 (UNDP)
人事専門官 HR Specialist
Office of Human Resources (OHR),
Bureau for Management Services (BMS)

- ◆今回訪問した国際機関
- 国連開発計画
- ▼国連開発計画(UNDP)は国連システムのグローバルな開発ネットワークとして、変革への啓発を行い、人々がより良い生活を築くべく、各国が知識・経験や資金にアクセスできるよう支援しています。
- ▼現在、約170の国で活動をし、グローバルな課題や国内の課題に対してそれぞれの国に合った解決策が見出せるよう取り組んでいます。
父が共産党政権下のポーランドからの難民であり、母が日本と韓国のハーフであったことから、国際情勢や国際機関に自然と関心を持つようになりました。
大学生の頃に参加した国連大学のグローバルセミナーにて「国際公務員になる為に必要なもの」が何か具体的にイメージできるようになり、将来のキャリアとして真剣に捉えるようになりました。
大学生当時の自分はこの「国際公務員になる為に必要なもの」は語学力、修士号、専門性だと思い、卒業後は海外の大学院に進学して現地で仕事を見つけようと考えました。
学部は明治大学の政治経済学部で学びました。政治経済学部には実践的な英語力を養成する講座が1年生時からあり、4年間を通じてこの講座に通い続けたことが語学力の基礎となっております。3・4年時の専攻は社会データの統計分析で、安藏ゼミという所に所属していました。
また、大学3年時にオーストラリアのアデレード大学に1年間交換留学しました。学部卒業後はイギリスのオックスフォード大学の大学院で社会学の修士号を取得しました。
学部時代の先生方が語学や統計分析の基礎トレーニングをしっかり行ってくれたことが、その後の大学院進学、イギリスでの就職に繋がったと思っており、先生方には大変感謝しております。
大学院卒業後は 、 会計コンサルティング会社デロイトのロンドン事務所に就職しました。Global Employer Servicesという多国籍企業の人事・税務コンサルティングを行う部門に所属し、イギリスで5年間、日本で1年半、オーストラリアで2年間の合計8年半働きました。
この部門はクライアントの人事戦略の策定を手伝ったり、組織再編による税務インパクトを計算したり、租税条約や判例を解釈して税務アドバイスを行う事などが主たる業務でした。
あっという間の8年半でしたが、ここで人事や税務の専門性及び多国籍なチームでの働き方を身につけることができました。
また、同期入社の同僚が様々な国の出身であったことや、3か国の事務所で働いた事で、複数の視点から物事を分析する習慣がつきました。

外務省が行っているJPO試験にてUNDP本部人事部に入りました。
2014年2月にニューヨークに来て、最初の配属先は人事部内の能力開発を担当する課で、UNDP内のリーダー育成プログラムや財務部のトレーニングプログラム等を担当しました。

現在の主な担当業務は人事データの分析や人事プロセスの効率化です。 人事業界は近年、ITシステムを導入して様々な業務を効率化すると共に多くのデータを集めて分析するという流れが加速しており、UNDPでも積極的にこれらを推進しています。
UNDPは160以上の国と地域で活動しており、多くの人事データは各国にあるUNDPのオフィスが収集して日々更新しています。
最近の分析ツールの発達のお陰で、これらの膨大なデータを様々な角度から分析できるようになり、戦略判断に役立てられるようになりました。
また、UNDPは大きな行政機関である為、どうしても複数の承認が必要なプロセスが数多く存在するのですが、ITシステムを活用してこれらのプロセスの効率化を進めています。
その他に大学・社会人向けのアウトリーチ業務も担当しており、大学等でUNDPで働く魅力や具体的な応募方法等の説明会も行っております。
私自身も学生の頃に国連職員から国際機関への就職について説明を受けたおかげで現在に至っているので、なるべく具体例を用いながら参加してくれた学生・社会人の方々が実際に応募してくれるように心がけて話しています
UNDPの主たる業務である貧困や環境問題、災害対応などにより多くの資金と人員が振り分けられるような、効率的な組織作りを目指して、今後も人事部内で様々なプロジェクトを携わっていきたいです。
また、もっと多くのLGBTIや障害を持つ方などがUNDPで働けるような仕組み作りも行っていきたいです。今年半年間ほど、ダスキン障害者リーダー育成海外派遣生として人事部に山本さんというギランバレー症候群を発症し身体障害を持つことになられた方が赴任され、一緒に働く機会に恵まれました。
元々民間企業の人事経験が豊富な方で、こういった優秀な人材がまだ多く埋もれていて、そういった人材をもっと活かせる仕組み作りが重要だと実感しました。
国際機関は特別な場所ではなく、志を持って入念な準備をすれば必ず入れます。

岡本さんとお話して、いくつかタメになるポイントをお話していだたきました。 英語は大学時代に日本で基礎をしっかり学んだとおっしゃっていたので、基礎はとても大事だと感じました。私もチアリーディングの基礎を日本でしっかり学んだことが自分の財産になっています。
もともと岡本さんは、高校生の頃は資格試験を目指していて、大学では法学部への入学を考えていたそうですが、日本の資格を取得すると日本でしか働けないのではないか(国際色豊かなキャリアを築けない)と不安に思うようになったそうです。本人も「今考えると、日本の資格を活かして海外で働くキャリア形成も可能なのですが」とおっしゃっていましたが、高校生の頃はそう考え、政治経済学部に入学したそうです。
そして、海外に行こうという考えのままイギリスの大学院に進学してそのままイギリスの会計事務所に就職したのが人生の分岐点だったとおっしゃっていました。20代に同期と友達感覚で一緒に働いたことが今にも繋がっていて、国連のオフィスにも自然に馴染めているそうです。これについても同感で、私もスポーツの取材をしていると、現場に馴染めるので、やはりまだ自分の思考が固まっていない若い頃の22歳や23歳に海外で働くのはキーポイントだと思います。
最後に、JPO試験については、専門性を決めるのが大変だったそうです。 国連は、オペレーション部門(管理業務)かプログラム部門(主に前線で貧困撲滅や難民支援等の様々な活動をする業務)にキャリア・パスが大きく分かれるため、どちらのキャリア・パスの入口を選ぶかが非常に大切とのことです。
多くの職員がはじめに入ったキャリア・パスで次の20−30年働くため、JPO試験受験時にはどのキャリア・パスで自分が将来にわたって働きたいかを真剣に考える必要があるそうです。岡本さんも最初はすごく迷ったそうです。その時に岡本さんの会社の先輩で国連に入った方に相談をしたそうです。一年に一度大きな会議の為のレポートを書いたり、複数年にわたるプロジェクトを管理するよりも、オペレーション部門はプロジェクトのタイムラインも短いものが多く、短期的に成果が評価されるし、そういった仕事の経験があるので、オペレーション部門の方がしっくりきて、自分にはあっているかなと思ったそうです。 これについても同感で、私も大学にチアリーディングかチアダンス部に入るか考えた時に、チアダンス部の方が入りやすいし、将来の夢(NFLチアリーダーになること)を考えたりしたときに、自分にしっくりきたのを覚えています。
岡本さんのように、若い頃に海外に出て、海外で活躍する日本人の方がもっと増えると 、 日本もさらに成長するかと思います。
「小池絵未のNY発国際機関探訪」VOL.13
出演:岡本カミンスキ健
国連開発計画(UNDP)Office of Human Resources (OHR) 人事専門官
取材地:ニューヨーク
2019年3月更新